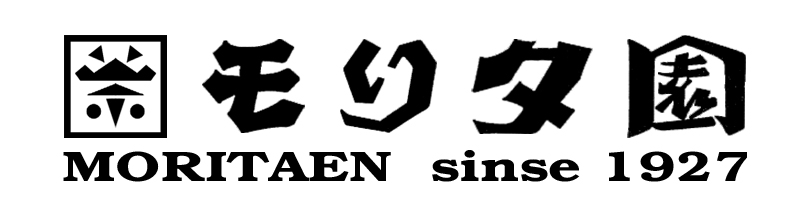贈り物にお茶を
退院祝/快気祝&お返し


A : 病気が全快したことをお祝いし、「お見舞いに来てくれた方」や「お見舞いを下さった方」にお礼の気持ちとして贈るのが快気祝いです。
近年では、お見舞いをいただいた方に対するお返しとする考え方が一般的、と考えられます。
のしの表書きには「快気祝」と漢字3文字で記入します。
A : インターネット上で検索すると様々な考え方があるようですが、 当店では、病気や怪我が全快した後、お見舞を頂いたかどうかとは関係なく、親しい人や近親者に報告を兼ねて品物を贈る際に 「快気内祝」を使う、と考えております。
のしの表書きには「快気内祝」と記入しますが、4文字で書くことを避けたい場合には、 「快気内祝い」と送り仮名をつける、あるいは「快気之内祝」と「之」を間に挟むなどして対応することもあるようです。
A : 快気祝いや快気内祝の品物には特に相場はないようです。お見舞いを いただいた方へ贈る場合には、お見舞いの1/2~1/3程度の金額を目安にするとよいと考えられます。単純な お見舞いのお返しをする場合も、この金額を目安にするとよいと思われます。

ギフト予算が決まっていらっしゃるお客様へ▼▼▼

ギフトの内容から検討されるお客様へ▼▼▼

全てのギフト商品をご覧になりたいお客様へ▼▼▼


テーマごとの商品群をご覧になりたいお客様へ▼▼▼

▽「茶通ぎふと」
|
▽「絢爛(けんらん)」
|
▽「悠々茶滴(ゆうゆうちゃてき)」
|
|
▽「十二単(じゅうにひとえ)」 
|
▽「TEABAG FOR YOU」  |
▽(参考)「プチギフト製作」  |


敬老の日に美味しいお茶を
● 今年、2018の敬老の日は「 9月17日 」です。
● 敬老の日とは老人を敬愛し、長寿を祝う日です。
● 「母の日」のように輸入された記念日と違い、日本以外の国にはありません。
------------------------------------------------------
敬老の日は、国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条によれば、
「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」ことを趣旨としている。
-----------------------------------------wikipedia「敬老の日」より
日本生命保険相互会社が「敬老の日」に関するアンケートを実施し、結果を公表しています。<平成25年9月13日付>
その内容(一部抜粋)によりますと・・・
Q:「敬老の日」にプレゼントを贈りますか?
贈 る⇒83.7%
贈らない⇒16.3%
(参考:「父の日」にプレゼントを贈る>51.8%)
Q:プレゼントは何を贈る予定ですか?
1位:食事・グルメ
2位:衣類・アクセサリー
3位:お菓子
Q:「敬老の日」のプレゼントにかける予算はいくらですか?
3,000円未満⇒29.2%
3,000円以上5,000円未満⇒35.6%
5,000円以上10,000円未満⇒25.8%
10,000円以上30,000円未満⇒8.1%
30,000円以上⇒1.5%
<出典: https://www.nissay.co.jp/news/2013/pdf/20130913b.pdf>
3,000円以上5,000円未満の品物を選ばれる方が多いようです。
また、ほどんどの方が10,000円未満でのギフトを考えていることが分かりますね♪
長寿のお祝いにお茶を
長寿のお祝いに美味しいお茶を・・・

こちらは
長寿を祝う節目には、
このような節目の年齢を 『 賀寿(がじゅ) 』 と呼びます。
満年齢 (数え年) |
名 称 | 名 称 の 由 来 (諸説あるものもございます。) |
| 60歳(61歳) | 還暦 (かんれき) |
還暦は干支が一巡(=十干十二支の組み合わせで60通り)して、生まれた年の干支に戻ってくるため「暦が還る」という意味で「還暦」と呼ばれます。 ※因みに、赤いちゃんちゃんこ・赤い頭巾・赤い座布団などを身に着けたりするのは、「赤子に還る」と言う意味合いだそうな。 (満60歳で祝う) |
| 65歳(66歳) | 緑寿(ろくじゅ) | 99歳・88歳・77歳の賀寿は一般的だったが、66歳の賀寿はもともと無かったので、2002年9月に日本百貨店協会が提唱して始まったそうです。 当て字は「緑」が「ろく」と読めることから66=緑緑となり、「緑々寿」を略して「緑寿」としたものです。 |
| 69歳(70歳) | 古稀または古希(こき) | 唐の詩人・杜甫が「人生七十 古来稀也」と言ったとされることに由来するそうです。 「人生70歳まで生きるということは、いにしえより稀なことである」 |
| 76歳(77歳) | 喜寿 | 「喜」を『草書体』で書くと、「七」を3つ三角に(「森」のように)重ねたカタチ(=㐂)になることに由来します。 |
| 79歳(80歳) | 傘寿(さんじゅ) | 「傘」をくずして書いた文字が、八と十を重ねた形になっていることに由来します。 |
| 87歳(88歳) | 米寿 | 「米」の字を分解してみると、「八・十・八」に分けられることに由来します。 |
| 89歳(90歳) | 卒寿(そつじゅ) | 「卒」のくずし字「卆」が、九十と読めることに由来します。 |
| 98歳(99歳) | 白寿 | 「百」から1画目の横線「一」を取る(100-1)と、「白」になる(=99)ことに由来します。 |
| 99歳(100歳) | 紀寿 | 「一世紀(=100年)」を表わす『紀』からとって紀寿とされているそうな。 |
| 107歳(108歳) | 茶寿(ちゃじゅ) | 「茶」の字を分解してみると、十・十(=20)、八・十・八(=88)に分けることができる(合計で108になる)ことに由来します。 |
| 110歳(111歳) | 皇寿(こうじゅ) |
「皇」は「白」と「王」に分解でき、「白」は白寿の「白」と同じく99。「王」は一・十・一とに分けることができる(合計で12になる)。 つまり…「白(=99)」+ 「王(=12)」=111となることからだそうな。 |
■還暦(かんれき)
男女ともに平均寿命が延び、高齢化が進んでいる現代において、
最初に迎える賀寿である『還暦』は長寿というより、
まだまだ現役の年齢かもしれませんから、「長寿」というよりも、
■還暦以外
本格的に長寿を祝う「古稀(70歳)」や「喜寿(77歳)」くらいからは、
■茶寿の御祝に美味しいお茶を…
由来としては「お茶」と関係がありませんが…