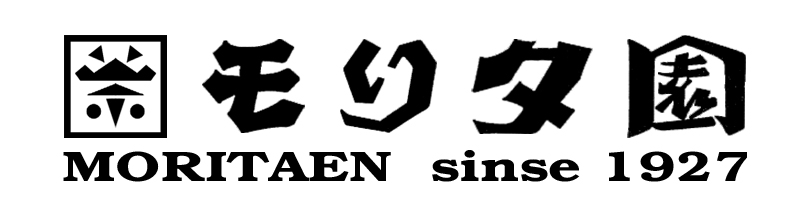お茶の製造と種類
製造工程の違い
 製造工程の違い
製造工程の違い
煎茶は、荒茶の製造工程で「味・香味・水色」が決まります。摘採後のすばやい熱処理と、その後繰り返される揉みによって、お茶の品質が大きく左右されます。

お茶は茶園で栽培し、適期に摘採した生葉を加工することによってお客様が目にする製品になります。茶葉は、摘み取った瞬間から「酸化酵素」の働きによって変化(発酵)が始まります。日本茶の場合、可能な限り新鮮な状態で「熱処理(蒸す・炒る)」をすることによって酸化酵素の活性を止め、葉の形状を整え、水分をある程度まで下げ、保存に耐えられる乾物状態にします。この乾物状態を荒茶といい、生葉から荒茶に仕上げる工程を荒茶製造(加工)と呼びます。荒茶は、形状が不揃いで水分含有量も多く、家庭での保存には適していません。また、香味のバランスもとれていないため、茶業者が消費地への出荷直前に仕上げ(再製)加工を行っています。
茶種と各製造工程の有無まとめ
製造する茶種によって荒茶製造の各工程がどのように違うのか、その有無を表にしてみました。
| 製 法 | 蒸し製 | 釜炒り製 | ||
| 茶 種 | 煎茶 | 碾茶 | 蒸し製 玉緑茶 |
釜炒り製 玉緑茶 |
| 製造工程 | ||||
| 蒸熱 ↓ |
● | ● | ● | - |
| 釜炒り ↓ |
- | - | - | ● |
| 冷却・葉打ち・粗揉 ↓ |
● | - | ● | ● |
| 揉捻 ↓ |
● | - | ● | ● |
| 中揉 ↓ |
● | - | ● | ● |
| 整揉 ↓ |
● | - | - | - |
| 乾燥 |
● | つる切り後 ● |
● | ● |
お茶の製造工程について詳しくは、
こちらにまとめました↓↓↓
以上です。
ご覧いただき有難うございます。
蒸し製玉緑茶と釜炒り製玉緑茶
<お茶の種類の解説ページ※商品の取り扱いはございません。>

蒸し製玉緑茶
嬉野茶(うれしのちゃ)などに代表されるお茶で、主に九州北・中部でつくられます。ぐりっと丸まった茶葉の形が特徴的なお茶です。

渋味が少なくまろやかな「蒸し製玉緑茶」
荒茶製造工程の途中までは煎茶と変わりませんが、精揉(最後に形を細長くまっすぐに整える)工程がなく、回転するドラムに茶葉を入れ熱風を通して茶葉を乾燥するため、撚れておらず、丸いぐりっとした形状に仕上がったお茶のことを「玉緑茶」と呼びます。「ムシグリ」「ぐり茶」とも呼ばれることもあります。
渋味が少なく、まろやかな味わいが特徴です。九州北部から中部でつくられ、佐賀の嬉野が代表的な産地です。(申し訳ございませんが、当店では蒸し製玉緑茶のお取扱いはございません。)
<お茶の種類の解説ページ※商品の取り扱いはございません。>

釜炒り製玉緑茶
生葉を蒸さずに高温の釜で炒り、丸い形状に仕上がったお茶のことです。

釜で炒った、丸い形状の「釜炒り玉緑茶」
釜伸び茶と同じように、「生葉を熱処理し、葉の形状を整え、水分をある程度まで下げて保存に耐えられる状態」にする荒茶製造加工において、釜で炒って製造しただけでなく、玉緑茶と同様に精揉(せいじゅう)工程がなく、回転するドラムに茶葉を入れ、熱風を通して茶葉を乾燥させたお茶が「釜炒り玉緑茶」です。精揉工程がないので、茶葉が撚れておらず、丸いぐりっとした形状に仕上がります。「釜で炒る」ことや「ぐりっ」とした形状の特徴から、「カマグリ」とも呼ばれます。(申し訳ございませんが、当店では蒸し製玉緑茶のお取扱いはございません。)
以上です。
ご覧いただきまして有難うございます。
~モリタ園~


番茶
<お茶の種類の解説ページ※商品の取り扱いはございません。>

番茶(ばんちゃ)
日本茶の基本的な主流から外れたお茶を総称して「番茶」と呼びます。茶葉の摘採期や品質、地域などによって、さまざまな意味の番茶があります。

番外のお茶、「番茶」
番茶は、「番外茶」からきているといわれており、大きく4種類に分類されます。
- 一番茶の手摘み、あるいは若芽を摘採した後の遅れ芽を摘採したもので、品質は良好。(専門的には「一茶番」)
- 三番茶を摘採せず、そのまま枝葉を伸ばしたものを秋に摘採したもので、量的にはもっとも多い。(専門的には「秋冬番茶」)
- 仕上げ加工工程で、大きく扁平な葉を切断せずに取り出し、製品化したもの。(専門的には「頭(あたま)」)
- 北海道、東北、北陸地方では、地方語として「ほうじ茶」のこと。
いずれにしても、摘採期、品質、地域などで日本茶の主流から外れた番外のお茶を指しています。
由来
番茶の名称の由来としては以下の2つの説が知られている。
- 番傘、おばんざい(御番菜)などの言葉に使われるように「番」には「普段の」「日常的な」という意味があるので、高級品ではない日常的に飲まれるお茶という意味で名づけられた。
- 一番茶、二番茶を摘んだあとの遅い時期に収穫される事から晩茶と呼ばれ、後に変化して番茶となった。
お茶の産地に限らず、根の強いチャノキは有用な境木としていろいろな地域で植えられていた。また、祭礼の際に植樹する風習がある地域もあり、そういった茶葉を利用して自家製の番茶は全国で作られていた。江戸時代の中期までは一般に出回る茶のほとんどは現在の基準で考えると番茶であったといわれている。製法や品質に対する工夫が施されて煎茶が出回るようになったのはそれ以降の時代になる。現在の番茶は煎茶の製法に準拠したものであるが、煎茶の製法が標準化されたのは比較的近年である。このため、各地に古くから伝わる伝統的な番茶には様々な製法で作られたものがあり、茶の木から葉を摘み取って自然乾燥させただけの薬草茶の様なものから中国茶のような発酵茶まで存在する。<引用元:Wikipedia「番茶」内記事「由来と歴史」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%AA%E8%8C%B6
>
ことわざ「鬼も十八、番茶も出花」とは?醜い鬼の娘であっても、十八と言う年頃になれば、色気が出て魅力的に見えるものだし、粗末な番茶であっても、一番茶は香りがよく美味しいということから。「出花」は、番茶や煎茶に湯をそそいだばかりのもの。昔は男女両方に言ったが、今は女性だけに使われる。『上方(京都)いろはかるた』の一つ。『上方(京都)いろはかるた』では「鬼も十八」。単に「番茶も出花」ともいう。醜い鬼や粗末な番茶に例えているのだから、他人の娘に対して使うのは失礼である。誤用例 「鬼も十八番茶も出花といいますが、娘さんもすっかりお綺麗になりましたね」<引用元:http://kotowaza-allguide.com/o/onimojyuuhachi.html>
以上です。
ご覧いただきまして有難うございます。
~モリタ園~
ほうじ茶と玄米茶

ほうじ茶(ほうじちゃ)
煎茶や茎茶などを使い、「炒る」ことで香ばしさが引き立ちます。

香ばしい香りの「ほうじ茶」
漢字で「焙茶」と表記されることもある「ほうじ茶」。煎茶、番茶、茎茶などをキツネ色になるまで強火で炒って(ほうじて)、香ばしさを引き出したお茶のことです。この他に、煎茶や番茶の仕上げ加工工程で選別した形の大きい葉や茎を混ぜ合わせ、炒った(ほうじた)ものも含まれます。ほうじ機でほうじ香が生じるまで約200度で加熱し、すぐに冷却されます。炒る(ほうじる)ことによってカフェインが昇華(固体から気体に直接変化する現象)して、香ばしさとすっきりとした軽い味が楽しめます。飲用やその効用
焙ずることで苦味成分のタンニン(カテキンなど)が壊れ、渋味や苦味が抑えられるので、口当たりは他のお茶よりもあっさりとしている。カフェインが少なく、胃への負担もあまりないことから、子供からお年寄り、病人まで、安心して飲用できるお茶である[6]。医者によっては、乳幼児の水分補給に勧めることもある。そういったことから、医療施設や介護施設ではほうじ茶が飲用されていることが多い。<引用元:Wikipedia「ほうじ茶」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BB%E3%81%86%E3%81%98%E8%8C%B6>
お好みの炒り加減で、美味しいほうじ茶をお手軽に。【 焙烙(ほうろく) 】
<お茶の種類の解説ページ※商品の取り扱いはございません。>

玄米茶
番茶や煎茶とほぼ同じ量の玄米を混ぜてつくられる玄米茶は、さっぱりとした味わいで、幅広い年代の方にお勧めできるお茶です。

炒り玄米の香ばしさが楽しめる「玄米茶」
水に浸して蒸した玄米を炒り、これに番茶や煎茶などをほぼ同量の割合で加えたお茶が「玄米茶」となります。炒り玄米の香ばしさと、番茶や煎茶のさっぱりとした味わいが楽しめます。玄米が混入していることで、煎茶や番茶の使用量が少なくなることから、カフェインが少なく、お子さまやお年寄りの方にもお勧めできるお茶です。
玄米茶
戦前に、鏡開きのときにできる餅屑を勿体無いと考えた茶商が、これを炒って茶葉に混ぜたのが始まりとされている。日本茶としては番茶やほうじ茶と同位に位置づけられ、高級な部類ではない。あっさりとしており、香ばしい香りと味が特徴。淹れるときには、沸騰した湯で短時間で抽出するのがコツである。時間をかけるとタンニンが出て渋くなる。玄米茶の品質は、茶葉よりもむしろ玄米の質に左右される。香ばしさは爆ぜた玄米よりも、狐色の炒った玄米のほうから出る。したがって、爆ぜた玄米の割合が多いものは粗悪品である。 玄米はもち米が用いられる事が多い。<引用元:Wikipedia「玄米茶」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%84%E7%B1%B3%E8%8C%B6>
以上です。
ご覧いただきまして有難うございます。
~モリタ園~


芽茶と柳
<お茶の種類の解説ページ※商品の取り扱いはございません。>
 芽茶(めちゃ)
芽茶(めちゃ)芽の先の細い部分を選別したお茶です。うま味を多く含み、味が濃く出るのが特徴です。

味が濃く、うま味たっぷりの「芽茶」
玉露や煎茶の仕上げ加工工程で、芽の先の細い部分を選別したお茶。高級茶の原料となる一番茶または二番茶から選別するため、お茶のうま味を多く含んでいます。芽茶の茶葉は小さく丸まっているのが特徴であり、丸みを帯びているものほど上質とされる。これは、芽や葉の先端は水分が多く柔らかいため、自然に丸まりやすいためです。茶葉が丸まっているため、おおよそ2煎目までが限界の茎茶や3~4煎目までが限界の煎茶と違い、茶葉が開ききるまで何度でもお茶を楽しむことが出来ます 。一方で、もともとの味が濃厚であるため、熱湯で淹れたり淹れる時間を長くしすぎるとお茶が濃くなりすぎることがあります。そのため、ぬるめのお湯で淹れるのが良いとされています。(当店では芽茶の取扱はございません。誠に申し訳ございません。)
<お茶の種類の解説ページ※商品の取り扱いはございません。>

柳または頭(頭柳)(やなぎ/あたま/あたまやなぎ)
仕上げ加工工程で選別された扁平なお茶です。

柳の葉のように扁平な「柳」または「頭」
やや硬化した葉が、柳の葉のように扁平に揉まれた茶葉を選別したものを、「柳」、「頭(あたま)」または「頭柳(あたまやなぎ)」と呼びます。商品名としても通用している「茎茶」や「粉茶」といった分類名称とは異なり、「柳」や「頭」は業界用語色が濃いような気がいたします。製造過程で出てきてしまう扁平な茶葉の総称ですので、原料は普通の煎茶と同じ生葉から出来ています。「番茶」と混同して認識されている場合もありますが、一番茶の選別で出る「柳」もありますので、一概に「柳=番茶」とは言い切れません。(当店では柳の取扱はございません。誠に申し訳ございません。)
以上です。
ご覧頂きまして誠に有難うございます。
~モリタ園~


茎茶と粉茶

茎茶(くきちゃ)
お茶の製造工程の一番最後=「仕上げ工程」で、新芽の茎だけを選別したお茶を茎茶と呼びます。

さわやかな香りと甘味をもつ「茎茶」
玉露や煎茶の仕上げ加工工程で、「選別機」を使用して「新芽の茎」だけを選別したお茶です。独特のさわやかな香りと甘味が特徴です。中でも玉露や高級な煎茶の茎は、「かりがね」と呼ばれて珍重されています。艶のある鮮やかな緑の茎茶ほど、甘味があります。赤褐色の太い茎は、機械刈りした硬い部分で、地域によっては「棒茶(ぼうちゃ)」として販売されています。

粉茶(こなちゃ)
細かな繊維や粉末を集めた茶なので、淹れたときに茶葉そのものも入りやすくなります。そのため、緑の色合いが鮮やかで、濃い味が特徴です。

細かな茶葉だけを選別した「粉茶」
玉露や煎茶の仕上げ加工工程で、廻しふるいなどで選別された細かい粉だけを抽出したお茶です。茶葉そのものが抽出液に多く含まれるので、水に溶けない有効成分を効率的に摂取することができます。お茶をいれた時の色合いは鮮やかな緑色で、味も濃く出ます。
以上です。
ご覧いただきまして誠に有難うございます。
~モリタ園~


抹茶と碾茶
<お茶の種類の解説ページ※商品の取り扱いはございません。>

抹茶(まっちゃ)
抹茶は碾茶を石臼で挽いて作ります。「茶の湯」でおなじみ。近年ではお茶として飲む以外にも、お菓子や料理などに利用されます。

茶の湯でおなじみの「抹茶」
碾茶を出荷する直前に石臼で挽いたものが「抹茶」です。お点前(おてまえ)における濃茶(こいちゃ)用の抹茶は、以前は樹齢100年以上という古木から摘採した茶葉が使われましたが、近年は濃茶に適した品種(さみどり・ごこう・あさひ・やぶきたなど)の選定や、肥培管理・被覆期間などの検討を行い、良質なものが濃茶用とされています。
飲料としての抹茶
黒味を帯びた濃緑色の濃茶(こいちゃ)と鮮やかな青緑色の薄茶(うすちゃ)がある。茶道では、濃茶は茶杓に山3杯を1人分として、たっぷりの抹茶に少量の湯を注ぎ、茶筅で練ったものを供する。薄茶は茶杓1杯半を1人分として、柄杓半杯の湯を入れ茶筅で撹拌する。茶道では茶を「点(た)てる」(点茶=てんちゃ)というが、濃茶は特に「練る」という。現在の茶道では、濃茶を「主」、薄茶を「副(そえ)」「略式」と捉えている。茶筅で撹拌する際に、流派によって点てかたが異なる。三千家ではそれぞれ、たっぷりと泡を立てるのが裏千家、うっすらと泡立てるのが表千家、もっとも泡が少ないのが武者小路千家といわれる。引用元:Wikipedia「抹茶」内記事「飲料としての抹茶」
<お茶の種類の解説ページ※商品の取り扱いはございません。>

碾茶(てんちゃ)
通常のお茶とは異なり、茶葉を揉まず、そのまま乾燥させた抹茶の原料となるお茶です。

抹茶の原料として用いられる「碾茶」
主に抹茶の原料となるお茶。玉露と同じように、茶園をヨシズやワラで覆い(被覆栽培)、日光をさえぎって育てた生葉(一番茶)を原料としますが、蒸した後、揉まずにそのまま乾燥し、茎や葉脈などを除いた後、細片が「てん茶(碾茶)」となります。一般に、玉露の被覆期間である20日前後より長く被覆されます。名称の「碾(てん)」は挽臼を表していて、挽臼で粉砕するためのお茶であることから「てん茶(碾茶)」と呼ばれます。出荷直前に石臼で挽いたものは抹茶として出荷されます。
「てんちゃ」違い・・・甜茶
甜茶(てんちゃ)とは、中国茶の中で植物学上の茶とは異なる木の葉から作られた甘いお茶の総称。古くからある薬草茶の一つ。バラ科キイチゴ属のテンヨウケンコウシ(甜葉懸鈎子) Rubus suavissimus S. Lee、アカネ科のギュウハクトウ(牛白籐) Oldenlandia hedyotidea、ブナ科のタスイカ(多穂柯)またはタスイセキカヨウ(多穂石柯葉) Lithocarpus polystachyus、アジサイ科(分類体系によってはユキノシタ科)アジサイ属のアマチャ(別名ドジョウサン、土常山) Hydrangea serrata (Thunb. ex Murray) Ser. var. thunbergii (Sieb.) H. Ohba 、ロウレンシュウキュウ(臘蓮繍球) Hydrangea aspera ssp. strigosa、ヤクシマアジサイ Hydrangea grosseserrata Engl.などの種を指す。引用元:Wikipedia「甜茶」
以上です。
ご覧いただきまして有難うございます。
~モリタ園~


玉露とかぶせ茶
<お茶の種類の解説ページ※商品の取り扱いはございません。>

玉露(ぎょくろ)
太陽の光を20日間程度さえぎって新芽を育てることで、渋味が少なく十分なうま味をもった味わいのお茶ができあがります。

豊富なうま味、独特の香りが特徴の「玉露」
新芽が2~3枚開き始めたころ、茶園をヨシズやワラで(最近は、寒冷紗などの化学繊維で覆うことも多くなっています。)20日間ほど覆い(被覆栽培)、日光をさえぎって育てたお茶が「玉露」になります。日光を制限して新芽を育てることにより、アミノ酸(テアニン)からカテキンへの生成が抑えられ、渋味が少なく、うま味が豊富な味になります。海苔に似た「 覆い香 」が特徴的です。同様に被覆栽培する緑茶として「かぶせ茶(冠茶)」がありますが、かぶせ茶は玉露よりも短い1週間前後の被覆期間です。玉露を作る茶木の品種
煎茶をはじめとする日本茶の多くは「 ヤブキタ 」が使用されているが、玉露は、「 オクミドリ 」、「 サエミドリ 」など、個性の強い品種が使われることが多い。玉露の呼び名自体に特に規定があるわけではなく、特に茶飲料の「玉露入り」に配合されている茶葉は、棚を作らず化学繊維で茶の木に直接カバーを掛け、かつ被覆日数の浅いかぶせ茶に近い物である場合も多い。
玉露の美味しい淹れ方
- 湯冷ましのため玉露の茶葉を入れていない常温の急須にお湯を注ぎます。
- 常温の急須にお湯注ぐことで沸騰しているお湯の温度が下がります。
- さらなる湯冷ましのため急須のお湯を湯飲みに注ぎます。
- 続いて急須に入れたお湯を茶碗へ注ぎます(急須から湯のみへお湯を注ぐことでさらに湯温を下げるのと同時に茶碗を温める効果もあります)。
- このとき茶碗の7~8分目くらい(約20ml)ほど入れて急須に残ったお湯はすべて捨てます。
- お湯の無くなった急須に玉露の茶葉を入れます。
- 茶碗にお湯を注ぎ急須に残ったお湯をすべて捨てた後、急須に玉露の茶葉を入れます。
- 茶葉の量は3人分で約10g(大さじで軽く2杯分)が目安です。
- 湯のみのお湯を茶葉の入った急須に注ぎます。
- 茶碗で湯冷まししたお湯を茶葉の入った急須へと入れます。この時点で適度に湯冷ましされたお湯が茶葉へ注がれるわけです。
- 約2分(上玉露は約2分半)、玉露の旨みをじっくり引き出します。
- 玉露の抽出時間は約2分(上玉露は約2分半)を目安にしてください。(適度に時間が経過したら急須の中を見て茶葉が開いているのを確認します。)
- 最後の一滴まで廻し注ぎしましょう。
- 味や濃さが均一になるように茶碗に均等に廻しつぎして最後の一滴まで出しきります(最後の一滴においしさが凝縮しています。お茶の味は最後の一滴で決まるとも言われています。)
- 2煎目も同様に湯冷まししたお湯を使用します。
- 2煎目は茶葉が開いている為抽出時間は30秒くらいで結構です。
<お茶の種類の解説ページ※商品の取り扱いはございません。>

かぶせ茶(かぶせちゃ)
太陽の光を1週間前後さえぎって新芽を育てることで、濃い緑茶の茶葉となり、うま味を感じるお茶ができあがります。

渋味が少なくうま味を多く含む「かぶせ茶」
「 冠茶 」と漢字で表記されることもある、かぶせ茶。玉露や碾茶が大きな遮光幕を茶園全体にさしかける方式であるのに対し、かぶせ茶は茶の木そのものに直接遮光幕をかけます。この遮光幕を直接木にかぶせる栽培方法が、「かぶせ茶」という名の由来です。ざっくり考えるならば、「煎茶と玉露の中間の栽培方法」がかぶせ茶の育て方ということになります。太陽の光をあてずに新芽を育てるため、茶葉の緑色が濃くなり、渋味が少なくうま味を多く含みます。同様に被覆栽培する緑茶として「玉露」がありますが、玉露はかぶせ茶よりも被覆期間が20日前後と長くなっています。
以上です。
ご覧いただきまして誠にありがとうございます。
~モリタ園~


煎茶と深蒸し煎茶
 煎茶 (せんちゃ sencha)
煎茶 (せんちゃ sencha)摘みたての新鮮な生葉を、蒸したり炒ったりして熱処理することで発酵を抑えた煎茶は、日本人に馴染み深いポピュラーなお茶です。

普段、もっとも飲まれているお茶、「煎茶」
煎茶は、緑茶の中で、もっともよく飲まれている代表的なお茶です。お茶は、茶園で栽培した生葉を加工することによって製品となります。生葉は、摘採した時点から酸化酵素の働きによって変化(発酵)が始まります。緑茶は摘採した生葉が新鮮な状態で熱処理(蒸す・炒る)することで酸化酵素の働きを止めて作る「不発酵茶」です。この「生葉を熱処理し、葉の形状を整え、水分をある程度まで下げて保存に耐えられる状態」にすることを「 荒茶製造 」といいます。「蒸して」、「揉んで」、「荒茶を製造する」もっとも一般的な製法でつくられたお茶を「煎茶」と呼びます。免疫力をアップさせる新たなお茶のいれかた 「氷水出し」
免疫力をアップさせる新たなお茶というものがあるんです。氷水で5分かけて淹れるととってもおいしくなるんです。緑茶を1日5杯以上飲む人の死亡率は男性で13%ダウン、女性で17%ダウンと言われているのもこの「カテキン」に抗酸化作用や抗がん作用があるからなんです。しかし氷水出しをするとテアニンは出てきますが、カテキンはほどんど出ないんです!カテキンの苦みがないために、氷水出しの方がうまみがより強く感じられるというわけなんです。また水出しの場合はカフェインがほとんど出てこないので、妊婦さんや小さなお子さん、授乳中のママでも安心して飲めるんだそうです!では健康成分はないの?というと「エピガロカテキン」という新健康成分が出ているということがわかりました。※エピガロカテキンとは?
エピガロカテキンを摂取すると体内の免疫細胞「マクロファージ」がとても活発になります。つまり感染症などの病気にかかりにくくなるんです。ガッテン流氷水出し緑茶の作り方ガッテン流氷水出し緑茶の作り方はこちらです!
<材料>
煎茶 10g
氷水 100ml
<作り方>
- 急須に氷水と茶葉を入れて5分待つだけ!
- 注ぐときは最後の一滴まで必ず注ぎ切るようにします。
深蒸し茶では苦みが出てしまうので、少し高級な煎茶がおすすめです。急須を冷蔵庫に保管しておくと1日以内であれば何度でも飲めます!なんと2煎目からは氷水をいれて5秒でOKなんです。
たくさん作りたい場合また、もっと手軽に大量に作りたい場合は・・
- 煎茶10gをだしパックに入れ氷水1リットルに入れ冷蔵庫に入れる。
- 30~40分したら冷蔵庫から出し軽くふって茶葉を取り出す。
本格的な味わい!エスプレッソ氷水出し緑茶本格的な味わいを楽しみたい時には「エスプレッソ氷水出し緑茶」のいれかたがおすすめです!「エスプレッソ」の名の通り、
- 煎茶の茶葉10gを用意します。
- 氷水40mlでいれる。
より香り高く、濃厚な旨味を楽しむことが出来ます。少しずつ、ゆっくり味わいながら飲みましょう♪
 深蒸し煎茶 (ふかむしせんちゃ hukamushisencha)
深蒸し煎茶 (ふかむしせんちゃ hukamushisencha)時間をかけて蒸されることで茶葉が細かくなるため、茶葉そのものの有効成分も体内に摂り入れることができます。

普通の煎茶よりも「 約2倍長い時間 」をかけて茶葉を蒸してつくったお茶を「 深蒸し煎茶 」または「 深蒸し緑茶 」と呼びます。茶葉の中まで十分に蒸気熱が伝わるため、柔らかくなった茶葉は揉まれる際に崩れやすくなり、形は細かめで、粉も多くなりますが、その分お茶の味や緑の水色(すいしょく)が濃く出ます。青臭みや渋味がとれて丸みのある味わいになり、また長時間蒸されることで茶葉が細かくなっているので、お茶をいれた際に茶葉そのものの粒子が多く含まれるので、水に溶けにくい有効成分も一緒に飲むことができます。NHK総合 2011年1月放送ためしてガッテン「お茶!がん死亡率激減!?超健康パワーの裏ワザ」
NHKためしてガッテンで上記の内容の番組が放送され、大きな話題となりました。番組の内容は
- 静岡県掛川市は、がんによる死亡率が日本一低く、高齢者の医療費も全国平均と比べて20パーセント以上も低い
- がん死亡率の低い町で上位にランクされるのは、静岡県の藤枝市や磐田市、浜松市、埼玉県所沢市、三重県の津市や鈴鹿市、鹿児島県の鹿屋市など緑茶生産地が多く含まれていた。
- お茶に含まれるカテキンが、がん予防効果があるのではないか?
- がん予防以外にも、緑茶には悪玉コレステロールを低下させたり、肥満防止、腸内環境改善の効果もある
緑茶を多く飲むというのは、習慣とするのに無理がなく、誰でも実践できますので、お薦め致します!
以上です。
ご覧いただきまして有難うございます。
~モリタ園~

緑茶の種類

緑茶の種類

国内で生産されるお茶は、ほとんどすべてが緑茶。その緑茶が、栽培方法、摘採時期、製造工程などの違いによって、さまざまな種類のお茶になります。

日本で生産されるお茶はほとんどすべてが「緑茶」
日本で生産されるお茶は、ほとんどすべてが「緑茶」です。※紅茶は?
昭和40年代までは、各地で紅茶が生産されていました(昭和40年で約1,500トン)が、品質・価格面でインド・スリランカに太刀うちできませんでした。
※烏龍茶は?
日本で烏龍茶がブームになった昭和54年(1979年)から60年(1985年)ころには、烏龍茶の製造を試みたところもありますが、紅茶同様に思わしくなかったようです。
日本茶(緑茶)の種類製法は、ほとんどが「 蒸し製法 」です。なお、九州の一部で地元消費のため「 釜炒り緑茶(玉緑茶など) 」が存在します。 茶種別生産量でみると、「 普通煎茶 」が3分の2を占めています。
下の1~15の各リンクから、茶種の詳細ページをご覧いただけます。
- 煎茶 (せんちゃ sencha)
- 深蒸し煎茶 (ふかむしせんちゃ hukamushicha)
- 茎茶 (くきちゃ kukicha)
- 芽茶 (めちゃ mecha)
- 粉茶 (こなちゃ konacha)
- 番茶 (ばんちゃ bancha)
- 柳 (やなぎ yanagi)/頭 (あたま atama)
- 焙じ茶 (ほうじちゃ houjicha)
- 玄米茶 (げんまいちゃ genmaicha)
- 玉露 (ぎょくろ gyokuro)
- かぶせ茶 (かぶせちゃ kabusecha)
- 碾茶 (てんちゃ tencha)
- 抹茶 (まっちゃ maccha)
- 蒸し製玉緑茶 (むしせいたまりょくちゃ mushiseitamaryokucha)
- 釜炒り製玉緑茶 (かまいりせいたまりょくちゃ kamairiseitamaryokucha)
以上です。
ご覧いただきまして有難うございます。
~モリタ園~